AIが万能かというと議論はある。
この記事では、片腕を失ったパラリンピックのスイマーがプロンプトで自分自身の絵を作ろうとしたが、どうしてもできなかったという話。まだまだ、こうした人のデータを学習していないからだという。しかし、こうしたことも可能になるのは時間の問題ではないだろうか?
ユーチューブチャンネル、登録お願いします!
BBCより、
AI couldn’t picture a woman like me – until now

まだAIでは描けない「わたし」:片腕の元パラ水泳選手が気づかせたAIの限界
AIは人間の創造力を超えた──そんな期待の裏で、まだ「描けない世界」がある。
BBCが報じたのは、片腕を失ったオーストラリアの元パラリンピック競泳選手**ジェス・スミス(Jess Smith)**の体験だ。
彼女がAI画像生成に挑戦したとき、AIは彼女の現実の姿を再現できなかった。
理由は単純で、AIの学習データに、彼女のような人の例が少なかったからだ。
AIが「片腕の女性」を描けなかった理由
ジェス・スミスは、自分の全身写真をAI画像生成ツールにアップロードし、「左腕が肘から先がない女性」という詳細なプロンプトを入力した。
しかし、出力されたのは両腕のある女性か、金属製の義手を装着した女性ばかり。
AIに理由を尋ねると、返ってきた答えはこうだった。
「十分なデータがありません。」
彼女はその言葉に衝撃を受けたという。
「AIは、私たちの社会を映す鏡だと気づきました。そこには、現実社会に存在する不平等や偏見も映り込んでいるのです。」
BBCの介入で“変化”が起きた
驚くべきことに、この問題はその後変化した。
BBCがOpenAIに理由を問い合わせたのち、ジェスが再度試したところ、ついに自分と同じ片腕の女性像を生成できたのだ。
「すごい、本当にできた!ついにアップデートされたんですね。」
彼女はBBCにそう語り、「技術の進歩を感じた」と喜びを表した。
OpenAIはBBCの取材に対し、
「最近、画像生成モデルに有意義な改善を加えた。公平な表現の課題はまだ残るが、学習後の調整や多様な事例の追加で改善を進めている。」
とコメントしている。
「見えること」こそがインクルージョンの第一歩
ジェスは語る。
「テクノロジーにおける“表現されること”とは、世界の一部として見てもらえること。
AIが包摂性を軸に進化するなら、それは人類にとっての進歩です。」
障害のある人々にとって、AIが“自分を正しく描ける”ことは単なる技術的課題ではない。
それは社会の中で「見える存在」になることそのものを意味している。
他の事例:片目の女性も「修正」されてしまう
記事ではもう一人、**ナオミ・ボウマン(Naomi Bowman)**の体験も紹介されている。
彼女は片方の目の視力を失っているが、AIに「背景をぼかすだけ」と頼んだところ、AIは彼女の顔を自動的に修正し、左右の目を“整えて”しまった。
「説明してもダメでした。AIには理解できなかったのです。」
ナオミは最初は笑い飛ばしたが、次第に悲しみを覚えたという。
「これはAIの中にある偏見を象徴しています。」
専門家の指摘:「誰がデータを作っているのか」
米国のCreate Labs社CEO、**アブラン・マルドナド(Abran Maldonado)**氏はこう指摘する。
「AIの多様性は、“誰がデータを作っているか”で決まる。
文化的に多様な人々がデータ構築に関与しない限り、AIは社会の盲点を再生産してしまう。」
2019年の米政府研究でも、顔認識AIが白人に比べてアジア系・黒人の識別精度が著しく低いことが明らかになっており、同じ構造が画像生成にも存在するという。
「不便なのは私ではなく、設計のほう」
ジェスは、自分を“障害者”とは考えていない。
「公衆トイレで、押し続けないと水が出ない蛇口がある。
それは私の能力の問題ではなく、設計者が私を想定していないから不便なんです。」
AIも同じだ。
多様な人を想定して設計されなければ、不便や排除を再生産してしまう。
まとめ:AIが「人間の多様さ」を学ぶ日
AIはすでに、かつて描けなかった「片腕の女性」を描けるようになった。
だが、それはゴールではなくスタート地点だ。
AIが本当の意味で人間を理解し、誰もが“見える存在”になるためには、
私たち人間がデータと倫理をアップデートする必要がある。
「AIが進化するとき、包摂性が中心にあれば、それは技術の進歩を超えて、人間性の進歩になる。」

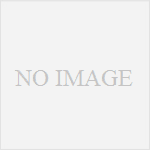
コメント