ホラー映画は恐ろしい。だが、人の不安な気持ちを和ませるという矛盾はなぜ起きるのだろうか?
それは、フィクションのホラーは私たちに、予測できないことへの対処の力を身につけさせてくれるからなのだという。
BBCより、
‘The paradox of horror’: How scary films can soothe your anxiety

「ホラー映画の矛盾 ― なぜ恐怖が不安を和らげるのか?」
導入:恐怖と安心の“逆説”
ホラー映画は人を怖がらせるもの――にもかかわらず、観ることで心が落ち着くという不思議な現象があります。
BBCの記事「The paradox of horror: How scary films can soothe your anxiety」では、この“恐怖のパラドックス”を科学的に解き明かしています。
論理的に考えれば、恐怖は危険を避けるために進化した感情のはず。それなのに、私たちは自ら恐怖を求めてホラーを観たがる――その理由は、**「予測できない出来事への耐性を高める訓練」**にあるのです。
1. 「恐怖」は脳のシミュレーション・トレーニング
モナシュ大学のマーク・ミラー博士によると、脳は常に世界を予測しようとする「予測エンジン」。
ホラー映画は“ちょうどいい不確実性”を与え、このエンジンを刺激して現実のストレスに強くなる訓練をしているといいます。
たとえば、恐怖映画を観ると心拍数が上がり、アドレナリンが分泌されますが、これは「安全な環境での危機体験」。
人はそこで、“怖いけれど乗り越えられる”という感覚を脳に学習させるのです。
2. 恐怖を楽しむ3つのタイプ
アリゾナ州立大学の心理学者コルタン・スクリヴナー氏は、ホラー好きの人を3つのタイプに分類しています。
- アドレナリン・ジャンキー
恐怖で“生きている実感”を得るタイプ。刺激を快感と感じる。 - ホワイトナックラー
怖さ自体は苦手だが、恐怖を克服することで自信を得るタイプ。 - ダーク・コーパー
現実の不安やストレスを軽減するためにホラーを観るタイプ。
特に「ダーク・コーパー」は、現実の恐怖に比べれば自分の生活は安全だと再認識し、安心感を得るといいます。
3. コロナ禍でも明らかになった「ホラー耐性効果」
スクリヴナー氏の研究では、ホラーファンはパンデミック中も冷静さを保つ傾向がありました。
「ニュースを落ち着いて受け止めている」「困難を乗り越える力を感じる」と答えた割合が高く、
恐怖を“安全に練習する”ことが、現実の危機におけるレジリエンス(回復力)を高めると考えられています。
4. “セラピーとしてのホラー”という可能性
スクリヴナー氏は、ホラーが心理療法にも応用できると述べています。
オランダでは、子どもの不安症治療に「MindLight」というホラー系ゲームを活用。
EEGヘッドセットで脳波を計測し、落ち着くほどゲーム内の光が強くなる仕組みで、恐怖を制御する訓練を行います。
この方法は認知行動療法と同等の効果を示しており、
「恐怖をコントロールする体験」こそが、不安を和らげる鍵であることがわかります。
5. 初心者へのおすすめ:「少し怖い」から始めよう
スクリヴナー氏は、ホラー初心者には「少しだけ怖い」作品を勧めています。
たとえば映画『シャイニング』のように、恐怖の中に芸術的・心理的要素がある作品が最適。
また、読書から入るのも良い方法です。文字ならば想像力をコントロールできるため、
“安全な恐怖体験”の第一歩にちょうどいいと言えるでしょう。
結論:ホラーは“心の筋トレ”
恐怖を感じながらも安全に過ごせるホラー映画は、不安に強くなるための心理的トレーニングなのです。
「恐怖を避けるのではなく、恐怖を使いこなす」
この発想が、現代社会を生き抜く新しいメンタル・スキルといえるでしょう。
ホラー映画を観てドキドキする夜は、実はあなたの心が“強くなる夜”なのかもしれません。

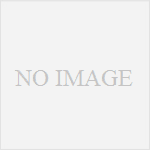
コメント