宇宙の軌道にある衛星から太陽光発電を行い地上に伝送する技術は何十年も前から提案されている。SFみたいな話だが、各国が盛んに研究をしている。宇宙空間での発電は地上の10倍になるということもあり、伝送技術の開発が鍵となっているのだ。
BBCより、
Space power: The dream of beaming solar energy from orbit

【タイトル】
宇宙から太陽光を地上へ送る「スペースパワー」:夢か現実か?
【リード文】
衛星や宇宙空間に展開した巨大太陽光発電設備から、無線で地上へ電力を送る構想――「宇宙太陽光発電(Space-based Solar Power, SBSP)」は、何十年も前からSFのように語られてきました。最近になって再び各国・各機関が具体的に研究・実証を進めており、地上の10倍とも言われる発電量や、伝送技術の課題などが改めて注目されています。ウィキペディア+2ABC+2
【本文構成】
1. 宇宙太陽光発電(SBSP)とは何か
宇宙空間(静止軌道・高高度軌道など)に太陽光パネルを設置し、地上よりも多く・安定的に太陽エネルギーを集め、マイクロ波やレーザーに変換して地上の受電設備(レクテナ/アンテナ)へ送るシステム。ウィキペディア+1
優位点としては、雲・大気・昼夜・季節変化の影響を大きく受けないため、地表設置型に比して発電量が数倍〜10倍になる可能性が指摘されています。ウィキペディア+1
ただし、打ち上げコスト、軌道上構造物の大規模展開・維持、安全性(ビーム伝送の影響含む)など、多くの技術・経済・規制の壁があります。ウィキペディア+1
2. 最新の研究・実証の動き
- 欧州宇宙機関(ESA)は「SOLARIS」プロジェクトを通じて、2030年代中の実証軌道ミッションを目指しています。ウィキペディア+1
- 英国のスタートアップなども、軌道上太陽光→無線伝送システムのプロトタイプ構築に向けた動きを報じられています。ザ・タイムズ+1
- 実験レベルでは、地上間のマイクロ波伝送実証(例えばハワイ間92 マイルの実験)など、ビーム伝送技術の検証が長年にわたり行われてきました。WIRED
3. なぜ「地上の10倍」も可能と言われるのか?
宇宙空間では大気の散乱・吸収・雲遮蔽・夜間・季節変動といった地上の太陽光発電の制限を大幅に減らせるため、理論上は地上設置型の数倍~10倍という発電性能が期待されてきました。ウィキペディア+1
ただし、「10倍」という数字はあくまで理論・モデル上のもので、実運用レベルでは多くの追加コスト・ロス要因が存在します。
4. 技術・実証・課題:現実を見ておこう
技術的課題
- 巨大構造物:数キロ/数十キロ規模のパネル展開が想定されており、打ち上げコスト・軌道利用・デブリ(宇宙ゴミ)リスクが重大。ウィキペディア
- 伝送技術:マイクロ波・レーザーで地上へビーム送信する必要があり、効率ロス・安全性(人体・飛行機などへの影響)・大気中伝播の影響が未解決です。arXiv+1
- 経済性:現段階では打ち上げコスト・建設・維持コストにより、地上太陽光よりも割高です。実用化・採算化にはコスト低減が鍵。ザ・ガーディアン+1
実証・時間軸
- 「実用化」という観点ではまだ初期段階。2040〜2050年代というスケジュールを提示する研究も。ザ・ガーディアン+1
- 補足:地上受電アンテナの巨大化、ビーム到達の法律・安全規制の整備など、社会インフラ的な課題も。
5. ファクトチェック:主張と実情
- 「何十年も前から提案されている」 → 事実。1960〜70年代に構想され、1973年には特許も出ています。ウィキペディア
- 「宇宙空間での発電は地上の10倍になる」 → 理論的には可能だが実証済みではない。「数倍〜10倍」といったモデル上の試算が多く、実運用ではコスト・ロスが増えるため慎重に評価すべき。
- 「各国が盛んに研究している」 → おおむね事実。ESA、英国企業、日本、中国等でプロトタイプ・研究が進んでいます。
- 伝送技術が鍵 → 正しい。ビーム伝送、受電インフラ、安全規制がボトルネック。
6. なぜ今、注目されているか?
- 再生可能エネルギー需要の高まりと「24時間・確実な発電源」への期待。
- 地上の太陽光・風力が立地・気象・夜間の影響を受ける中、宇宙なら“常時日照”に近づけるという魅力。
- 発射コスト低下・衛星製造技術の進化・小型衛星・ロボティクスの発展により、かつて“夢”だった概念が現実味を帯びてきた。
【まとめ】
宇宙から太陽光を地上に届ける「スペースパワー」は、SFの世界から現実の研究テーマへと移りつつあります。ですが、現時点では「いつでもどこでも使える」という実用段階には至っておらず、コスト・技術・法規制という巨大な壁が残っています。
- 理論上は“地上の数倍〜10倍発電”“気象影響なし”“地球規模の電力供給”という可能性あり。
- しかし実証段階では、打ち上げコスト・送電ロス・受電設備・安全性・経済性が制約。
- 今後10〜20年で、プロトタイプ→実証→商用化という段階に進む可能性があります。
おおいなる夢ですが、着実に足下から積み重ねられている「未来の発電源」というわけです。

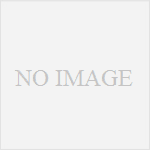
コメント